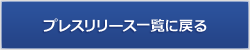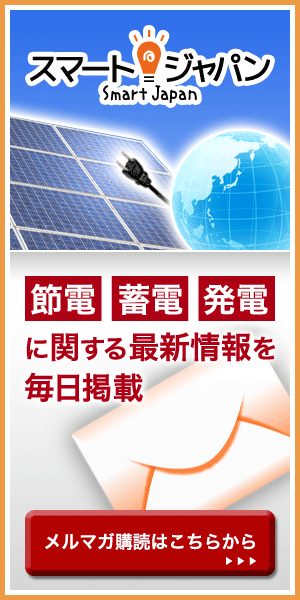プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
FCトラック・バスなど、燃料電池システムの世界市場を調査
第25088号
FCトラック・バスなど、燃料電池システムの世界市場を調査
― 2040年度市場予測(2024年度比) ―
●FCトラック・バス(トラック・バス向け燃料電池)
[世界]3兆6,252億円(31.8倍) [日本]1,360億円(90.7倍)
航続可能距離や車両重量の課題を解決できるシステムとして注目が集まる
コスト低減や水素インフラの構築が進むことにより市場拡大
◆燃料電池システムの世界市場 18兆2,264億円(45.0倍)
乗用車、商用車から始まり、スタック多様化で建機・農機や船舶など様々な用途を開拓
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋 社長 菊地 弘幸 03-3241-3470)は、FCV向けで進めてきた技術開発が高度に進化し、今後は水素社会の形成やカーボンニュートラルの実現に向け多用途展開が期待される燃料電池関連の市場を調査した。その結果を「2025年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望」にまとめた。
この調査では燃料電池システム8品目、スタック部品10品目について、最新の市場動向をまとめ将来を展望した。また、燃料電池の多用途化に向けて課題となる水素供給設備の整備状況や、各国の政策、アライアンス動向についても調査した。
◆注目市場
●FCトラック・バス(トラック・バス向け燃料電池)
トラックやバスの駆動用電源として使用される燃料電池(FC)システムを対象とする。
2025年度の世界市場は1,044億円が見込まれる。足元では車両や燃料の価格が高いことや水素インフラ不足のため、大きな伸びにはなっていないが、長距離走行・大型車両が想定されるトラック・バスは燃料電池の利用が有望視されている。
トラック・バスの電動化には航続可能距離や車両総重量などの課題があるが、燃料電池駆動にすることで、これら課題を解決できる可能性がある。そのため、FC車両の開発の重点を乗用車から商用車へ転換する動きが世界的にみられ、市場は2030年度以降大きく拡大すると予想される。CO2排出車両の規制厳格化によるペナルティや車両導入・燃料費に対する補助金などのインセンティブも導入を後押しするとみられる。
FCトラック・バスの普及には水素インフラの構築が必要不可欠であり、世界的に2010年代後半より水素ステーションの整備が進められてきた。しかし、水素需要の停滞による原料コストの上昇や水素ステーションの老朽化といった課題があり、国や地方自治体では政策や補助などでのサポートを進めている。
現状、アジアが需要の大半を占め、特に中国がけん引しているほか、韓国でも導入が増えている。中国は、FC商用車の導入数で世界トップとなっている。中長期計画として、2025年で5万台、2035年には100万台の導入を計画しており、モデル都市群を中心にFCトラックの導入が進んでいる。FCバスの導入拡大に向けては、従来のバスの廃棄・切り替えに伴う補助金の引き上げなどを含んだ政策が2025年に開始するなど支援が進んでいる。中国市場に対し、日本や米国、欧州メーカーも参入を進め、早期の事業化を目指していくとみられる。
韓国は、2018年より水素社会形成へ向けた意欲的な取り組みがみられる。自動車メーカー大手の現代自動車からFCトラック・バスがラインアップされ2024年にはFCバス約1,000台が導入されるなど、市場が急拡大した。中国企業のシェアが高いEVバスへの補助を縮小し、現代自動車が展開するFCバスへ補助を手厚くすることで導入が促進されている。
日本では、国内自動車メーカー5社が共同出資したCommercial Japan Partnership Technologies(CJPT)により小型FCトラックの導入と大型FCトラックの実証が行われている。小型FCトラックでいすゞ自動車とトヨタ自動車が、大型FCトラックでは日野自動車とトヨタ自動車が共同開発した車両の導入・実証が進められている。
●産業・業務用燃料電池
商業施設、オフィスビル、工場、データセンターなどのユーザーが自家発電設備(一部BCP用途)として導入するものと、発電事業者が売電を目的に導入する燃料電池を対象とする。
米国と韓国で導入が進んでおり、2大市場を形成している。米国では導入インセンティブにより工場や小売店舗、データセンターへの導入が進んできた。AI関連の設備投資拡大に伴うデータセンター需要の増加から電力需給バランスへの影響が懸念されている。5年以内に容量ベースで50GW以上のデータセンターが建設されるとの見通しもあり、比較的短い施工期間でオンサイト発電が可能な低炭素電源である燃料電池のニーズが拡大するとみられる。
韓国は発電用が市場の大半を占めており、各種補助金や義務制度を背景に導入が進んできた。2023年よりクリーン水素発電義務化制度(CHPS)がスタートし、入札での導入が進められている。2040年には累積8GWを導入目標としており、市場拡大が期待される。
日本は、業務用燃料電池の補助金終了の影響もあり、近年導入が減少している。現状では具体的な動きは見られないが、再生可能エネルギー導入の中で系統不安を抱える地域や、データセンターを中心に電力需要の拡大が見込まれる地域、水素インフラの普及に注力する地域などにおいて普及が期待される。各種法規制や水素価格、水素貯蔵・供給設備の構築などの課題があるが、業界団体による規制緩和の提言が進められているほか、各種プロジェクトの進展により徐々に改善が進むとみられる。
●FCV(FC乗用車)
燃料電池システムを主要動力源として搭載する乗用車(タクシーも含む)を対象とし、燃料電池システムと充電可能な駆動用バッテリーを併用したプラグインFCV(PFCV)を含む。市場は燃料電池システムを含む車体価格で算出している。
EVの低価格化や水素ステーションなどのインフラ問題、水素価格の高止まりなどから2024年度の市場は縮小した。FCトラック・バスの先行普及により、FCVでも車両性能の向上や価格の引き下げ、水素ステーションの整備といった普及への素地が整うことで将来的な市場成長が期待される。市場は2035年度には3兆円、2040年度には10兆円を超えると予測される。
日本では、国内自動車メーカー5社が共同出資したCommercial Japan Partnership Technologies(CJPT)により小型FCトラックの導入と大型FCトラックの実証が行われている。小型FCトラックでいすゞ自動車とトヨタ自動車が、大型FCトラックでは日野自動車とトヨタ自動車が共同開発した車両の導入・実証が進められている。
◆調査結果の概要
■燃料電池システムの世界市場
PEFCはFCV、FCトラック・バスなどの移動体が主な需要先であり、FCトラック・バス向けが最大の規模である。日本や韓国の自動車メーカーでは、量産化されたスタックを乗用車以外の用途に展開する動きが活発で、船舶や鉄道などの大型駆動用、定置用燃料電池へ広がる事例も多数登場している。今後多用途化により市場は大きく拡大していき、量産によって低コスト化も期待される。
SOFCは、2025年度時点では95%以上が産業・業務用燃料電池向けであり、一部家庭用燃料電池向けも見られる。量産メーカーが限定されており、普及に向けてはコストの高止まりが障壁となっているが、船舶やSOEC(固体酸化物型電解セル)など多用途展開を含めた量産体制の構築や、セルスタックの開発・材料代替、生産委託などによりコストの低減が図られている。近年メタル支持型セルスタックの量産化も進められており、これの採用によって600℃程度の低温作動化やコスト低減、移動体への導入などが期待される。
◆調査対象
燃料電池システム・FCV(FC乗用車)
・FCトラック・バス
・燃料電池産業用車両
・燃料電池大型駆動用
・燃料電池小型駆動用
・産業・業務用燃料電池
・家庭用燃料電池
・ポータブル/バックアップ用燃料電池
スタック部品
PEFC
・PEFCスタック
・PEFC電極材
・PEFC電解質
・PEFCセパレーター
・PEFC GDL
SOFC
・SOFCスタック
・SOFC燃料極(アノード)
・SOFC空気極(カソード)
・SOFC電解質
・SOFC金属インターコネクタ
2025/9/2
対象レポート
関連レポート
上記の内容は弊社独自調査の結果に基づきます。また、内容は予告なく変更される場合があります。上記レポートのご購入および内容に関するご質問はお問い合わせフォームをご利用ください、報道関係者の方は富士経済グループ本社 広報部(TEL 03-3241-3473)までご連絡をお願いいたします。
- 北海道豊富町 未利用天然ガスを活用したDMR水素製造プラントが完成 〜 国内初のDMR(メタン直接改質)法によるCO2フリー水素の商用規模生産を通じ、地域CO2フリー水素サプライチェーンの社会実装を目指す 〜 〔09/19 エア・ウォーター〕
- EVバス導入によるGX推進事業補助金 〔09/18 沖縄県庁〕
- 洋上風力発電事業に関する国への要望について 〔09/18 千葉県庁〕
- 「日本初の浮体式洋上風力発電所」をテーマにしたRICEメディアとのタイアップ動画を公開 〔09/18 戸田建設〕
- 南フランス・核融合実験炉イーター向けダイバータ外側垂直ターゲット20基を新たに受注 〔09/18 三菱重工業〕
- 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 〔09/18 東京電力ホールディングス〕
- 佐久間ダム貯水池の作業船沈没について 〔09/18 電源開発〕
- 従業員の「挑戦と成長」を後押しするための人事関連制度の導入・拡充~ キャリア支援・成長機会の強化およびライフサポート施策の充実~ 〔09/18 大阪瓦斯〕
- 福島第一原子力発電所における体調不良者の発生について(続報2) 〔09/18 東京電力ホールディングス〕
- 「くらしTEPCOポイント」から「JRE POINT」へのポイント交換サービスを開始します 〔09/17 東日本旅客鉄道〕
情報提供:JPubb