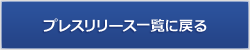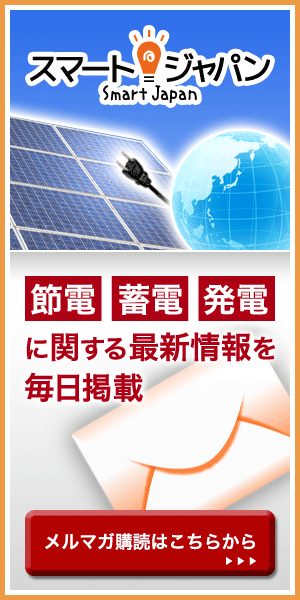プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
新潟県知事 定例記者会見 2025年04月09日 - ●「新潟県多様で柔軟な働き方●女性活躍実践企業認定制度」の愛称及びロゴマーク募集 ●柏崎刈羽原発 ●主要地方道 松代高柳線(柏崎市高柳町門出地内)における道路崩落 ●トランプ政権の関税措置 ●県営高田発電所の水圧管路の破断
令和7年4月9日 新潟県知事 定例記者会見
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0739874更新日:2025年4月10日更新
(記者会見の動画を新潟県公式Youtubeチャンネルでご覧になれます)<外部リンク>
1 日時 令和7年4月9日(水) 10時03分~10時43分
2 場所 記者会見室
3 知事発表項目
・「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」の愛称及びロゴマーク募集について
4 質疑項目
・柏崎刈羽原発について
・主要地方道 松代高柳線(柏崎市高柳町門出地内)における道路崩落について
・トランプ政権の関税措置について
・県営高田発電所の水圧管路の破断について
知事発表
(「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」の愛称及びロゴマーク募集について)
ご承知の通り、ハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)登録制度というものを、県はこれまで運営していまして、男女共同参画を進める、そうした取り組みを進めている企業を登録する形で、後押しをしてきたところでありますが、育児休業、介護休業など、いろいろな制度も変わってきて、さらに一層、若い世代、女性も含めて、若い世代に新潟を選んでもらえるように、選ばれる新潟ということを言ってきましたけれども、働く場所として、新潟を選んでいただけるように、環境をより魅力的なものにしていく必要があるということで、今年度からハッピー・パートナー企業登録制度を見直しまして、新たに「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」をスタートさせたところであります。ただ、今申し上げたように、少し名前が長いので、これではなかなか身近に感じていただけないということもあり、新たに愛称とロゴマークを募集したいと思っています。詳しくはこの後、事務局の方からブリーフィングさせていただきたいと思います。私からは以上です。
(資料)「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」の愛称及びロゴマークを募集します [PDFファイル/980KB]
質疑
Q 新潟日報(代表幹事)
東京電力柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う県民投票条例案について伺います。知事は「再稼働の是非は『賛成』または『反対』の二者択一の選択肢では、県民の多様な意見を把握できない」などとする意見を公表されました。今後は県議会での審議に移ることになりますが、知事としては今回の県民投票の実現は難しいというご認識でしょうか。それとも、他のご認識がありますでしょうか。お願いいたします。
A 知事
知事の意見というのは先日(4月8日)公表した通りですので、あとは、条例の制定、改廃の権限は議会にございますので、議会の議論を十分に行っていただきたいと思います。
Q 新潟日報(代表幹事)
知事のご認識としては、今回、県民投票はなかなか難しいのではないか、実現は難しいのではないかという・・・。
A 知事
条例が制定されるかどうかについては、議会の議論ですので、私から特にコメントすることはないのですけれども、しっかり執行部としても対応したいと思います。
Q UX
過去、県民投票条例が直接請求された事例を見ると、知事から、賛成もしくは反対と明確に示した事例もあれば、賛否を明らかにしなかったという、三様あるのですけれども、知事は今回、明らかにしなかった理由・・・。
A 知事
私自身は住民投票という制度自体は、否定するものではなくて、間接民主制が地方自治の今原則ですけれども、それを補完するものとして、直接的な民主主義の一つの手段と理解していますし、住民投票そのものを、そういった意味では評価をしているつもりなのですけれども、ただ、この原発の再稼働という問題について、私はいろいろな材料を揃えて、順次材料を揃えて、県民の中で議論を進めている、これは皆さんも承知していただいていると。議論を深めていく過程で、県民がどういった受け止めをするのか、この原発とどう向き合うと考えるのかを探ります、見極めていきますと、こう申し上げています。見極めるという手段、見極めという段階において、この住民投票については、やはり課題があると。二者択一で得られる情報というのは、限られてくるという中で、課題があるというのが、私の意見です。
Q 新潟日報
知事は先週(4月2日)の会見で、二者択一のことについて、マルかバツなので、得られる情報がどうなのか、考えどころだと先週仰っていたのですけれども、そこからこの意見を、昨日公表されたわけですけれども、どういった考えを踏んで、この結論といいますか・・・。
A 知事
私の思考のプロセスを解説することはできませんけれども、まさに先週のご質問でいただいたことに答えた気持ちが変わらなかったということですよね。
Q 新潟日報
多様な意見を把握するというところにおいて・・・。
A 知事
県民の中には、多様な意見があると私は思っていて、それはこれまでいろいろな、寄せられた県民の便りなど、それからいろいろな地域の声を聞いてくる中で、本当に絶対反対という人から、絶対賛成という人まで、かなり幅があって、それぞれこういった状況ができるのならいいのになとか、こういった条件、不安が解消されないのなら、やはり反対だとか、本当に気になっていることは、それを先週の記者会見で悩み、悩んでいる、逡巡しているという言葉を使ったのかもしれませんけれども、そういった人たちが大勢いると思うのです。それが多数だと思うのですけれども、どこにその課題があるのか、何が悩みなり、不安の種なのかという辺りも、そこを拾っていくことが、行政なり、政治の仕事だと私は思っていまして、そこに解決の道ができるのなら、県民の意思というのは、受け止める気持ちというのは、自ずと固まっていくのではないかと思っています。
Q 新潟日報
そういった悩んでいる人であったり、そういった方々の意見をこれから捉えていくために、今回、県民投票ではなかなか難しいのではないかという、難しいといいますか、把握ができないのではないかというご意見だと思うのですけれども、知事、かねてから公聴会ですとか、首長との対話ということを挙げてきましたけれども、多様な意見を把握するという意味で、今どういったことを考えて・・・。
A 知事
これまでも申し上げた公聴会とそれから首長との対話、意見交換は、これはもう当然と思っていますし、その他に、もちろん、先ほど申し上げたように、随時いろいろなご意見は県民の便りという形でいただいていますし、その他、意識調査をやるなど、考えられる方法あると思います。それは、今検討していまして、このようなことをやっていこうというのは、いずれ材料が全部揃って、議論が深まっていく中で、皆さんに、今後はこういった形で意見を集約していきますというようなことをお示しすることができる段階がくると思います。
Q 新潟日報
4月になって、いろいろな材料が、1つ、2つ出てきたとは思う・・・。
A 知事
大分、議論の材料と私が言っていたものは揃ってきましたけれども、あと、原子力規制委員会での原子力災害対策指針の見直しの作業の最終形がもうすぐ出てくると思いますし、あとは、シミュレーションの結果もそろそろ出てくると思いますので、あと1つ、2つ程度は、議論の材料になるものがあると思うのですけれども、その材料が出てくるのと並行して、議論は進めながら、次には意見を、県民の気持ちを把握していく、見極めていくためのプロセスをお示ししたいと思っています。
Q 新潟日報
それは県民の意識調査という話もアイデアの一つとして・・・。
A 知事
アイデアの一つとしてはあります。
Q 新潟日報
言及されたと思うのですけども、そういったように県民投票という手段ではなくて、県民に直接、意見を聞くといいますか、そういった方法も考えていらっしゃるということなのでしょうか。
A 知事
県民の意見を聞くということはそういったことですよね。首長を通して聞くというのも、もちろんそうですし、それは公聴会という、これは直接的に聞く話ですし、アイデアとしての意識調査ですとか、あるいは、もともと県民の便りを随時いただいていますので、そうしたものも、当然、判断の材料になると思います。
Q 新潟日報
意識調査ということは、あまり知事、言及されてこなかったように・・・。
A 知事
いろいろな報道機関も調査されていますので、そうしたものでも十分という議論もあるかもしれませんし、そこは今いろいろと考えていく・・・。
Q 新潟日報
いずれ材料が揃った段階で、そういったもののプロセスについて説明する・・・。
A 知事
そこで言う材料というのは、見極めていく材料、議論の材料・・・。
Q 新潟日報
議論の材料・・・。
A 知事
議論の材料はあと1つ、2つだと思いますけれども、そうしたものが揃い、議論が深まっていく中で、どこかでそれを今度は見極めていくプロセスに入るというつもりです。
Q 毎日新聞
今、意識調査、報道機関がやるような調査もあるというふうに・・・。
A 知事
もうやられていますよねと言ったのです。
Q 毎日新聞
仰いましたけれども、今回、県民が納得するプロセスというのが必要だと思うのですが、県民が納得するような・・・。
A 知事
納得という意味は分かりませんが、私はそうやって県民の意思を見極めた上で、リーダーとしての結論を出しますと言っているのです。その出した結論について、県民の意思を確認しますとこう申し上げているので、その意思を確認するところが納得ということなのかもしれませんね。
Q 毎日新聞
そうすると、この意見書を受けて、自民党ではない、第2会派、第3会派の中から、知事が例示された公聴会であるとか、首長との対話に関しては、限られた声でしかないのではないかと。公聴会であっても、1回に100人、200人ほどしか、参加できないので、それだったら県民投票の方が二択ではあるけれども、多くの県民の大まかな意思は確認できるのではないかと仰る方たちがいるのですけれども・・・。
A 知事
県議会でそういった質問が出たらお答えしますけれども、今、この記者会見で質問が出たので、私は二者択一では得られる情報が少ないと思います。
Q 毎日新聞
知事は民意の、多様な民意が反映しにくいということを意見書でも仰っています。
A 知事
多様な意見を把握できない・・・。
Q 毎日新聞
把握できないと仰っていますし、意見書にもそういった趣旨のことを書いていらっしゃいますけれども、民意が反映されることというのは、確かに必要だと思うのですけれども、一方で、民意といいいますか、県民が選択する機会というのも・・・。
A 知事
ですので、先ほどからお答えしたではないですか。
Q 毎日新聞
信を問うというのは・・・。
A 知事
私が出した結論について、県民の意思を確認すると言いました。
Q 毎日新聞
結局、その意思を確認する方法としては、県議会でも、信を問うというお言葉を仰って・・・。
A 知事
意思を確認する方法は、今決めたものはありませんが、かねてから私は信を問う方法は最も明確で重いと申し上げています。
Q 毎日新聞
その信を問う方法というのはまだ決めていらっしゃらない。
A 知事
普通、常識的に信を問うと言えば、皆さん想定されるものがあるわけですよね。
Q 毎日新聞
普通は選挙・・・。
A 知事
公職であれば選挙を想定するでしょうし、もう少し厳密にといいますか、言い方としては、信を問うとは、これも以前の会見でお答えしていると思いますけど、存在をかけるという、まさに、信任、不信任の意味合いがあると思うのですよね。そういった形での結論、リーダーが出した結論に対する県民の意思の確認という方法が最も明確で重いと思います。
Q 毎日新聞
信任、不信任となると、やはりまさに選挙という・・・。
A 知事
選挙が通例だと思いますが、信任、不信任、その諮り方、やり方にはいろいろあると思います。存在がかかるという意味では、議会の信任、不信任ももちろんそうです。それを投票でやるという方法もないことはないのかもしれませんけれども。
Q 毎日新聞
いずれにしても、任期がもうあと来年(令和8年)の6月に迫っているという状況があって、来年の6月には間違いなく知事選挙が行われるわけですけれども、知事選挙もあると仰いましたが、それも否定されない、知事選挙で・・・。
A 知事
決めたものはありません。
Q 共同通信
県民投票条例について伺います。先ほど冒頭の質問に対して、条例の制定とか、改廃の権限は議会にあるということで、特にコメントすることはないというようなお話だったと思うのですけれども、昨日公表された意見書を見ると、やはり今回の条例案に関しては否定的といいますか、難しい慎重な立場なのかと思うのですけれども・・・。
A 知事
それは皆さんの解釈です。私の書いた意見は、あれ以上でもあれ以下でもないです。
Q 共同通信
特に否定的な見方でもない・・・。
A 知事
そこは評価の問題なので、私がコメントということではないです。
Q 日経新聞
先ほどお話をされた、いろいろな意見を収集するというところの話なのですけれども、東京都知事選などで、AIを使ったもの、ブロードリスニングといったような手法が最近使われる事例が目立ってきて・・・。
A 知事
AIを使った・・・。
Q 日経新聞
ブロードリスニングという、いろいろな意見、どういった情報が多いかといったところを分析する・・・。
A 知事
ネット上で、SNSなどに出ている発言なり、文書を拾ってくるという・・・。
Q 日経新聞
そういったことを考えてらっしゃるのか・・・。
A 知事
そこは少なくとも現時点で私は想定していなかったのですけれども、ネット上で溢れる様々な文書というのが、どれほど思いが詰まっているのかというところも、もちろん分かりませんし、ましてやそれが新潟県民の声なのかどうかも分からないのです。
Q 日経新聞
むしろイメージとしては、例えば各家庭にアンケート用紙のようなものを送って回答など、そういったイメージ・・・。
A 知事
それも意識調査としてはあるのかもしれませんけれども、相当なコストと手間がかかりますね。
Q 日経新聞
どういったイメージを、今のところされていらっしゃるのか・・・。
A 知事
公聴会と首長との対話というのは、これはこれまでも申し上げてきたことですし、詰めていきたいと思いますけれども、何度も先ほどから繰り返し言っているのですけれども、便りというのは、こちらに本当に大勢寄せられますので、それももちろん、県民の受け止めを見極める方法の一つ、手段の一つですよね。それに加えて、どういった形で県民の受け止めを探っていくのか、見極めていくのかを、先ほどから申し上げたように、意識調査など、もっとやり方があるのか、それは今検討をしています。
Q 日経新聞
公聴会の開き方として、できるだけ幅広い意見を集めていくというところを達成するための開き方といいますか、要するにどういった方々に出席をしてもらうような・・・。
A 知事
それも今、事務的に検討してもらっています。
Q 日経新聞
各地で開いていくというようなイメージで・・・。
A 知事
何回か開くのだろうと思いますけれども、やり方については、今検討中です。
Q 日経新聞
基本的に当然、来年の6月頃までには何らかの、少なくとも皆さんの考えていることを聞くというようなところはやられるのかと思っているのですけれども、およそいつ頃を目安として・・・。
A 知事
それは先ほどのご質問に答えたように、いずれ、そうした意見を集約していくプロセスに入ると思います。ただそれを、今この時点で、いつから、何を、これをやりますなど、そこまでは詰まっていません。
Q NHK
今回、知事意見としては課題を提示する形になっていると思うのですけれども、県議会の中で、提示した課題に関して、どのような議論を期待したいなど・・・。
A 知事
それはもう議会のまさに権能ですので、私はこういったことをしてほしいなどということはおこがましいので、申し上げることはありません。知事の意見というのは、お付けしましたので、あとは元々、この直接請求というのは、議会に向けられているので、もちろん首長を経由して出るのですけれども、議会でしっかり受け止めて、ご議論いただきたいと思います。
Q NHK
意見を読ませていただきまして、二者択一では、県民の多様な意見の把握が難しいというところに対して、一方で、先ほどの公聴会であるとか、首長への意見を聞く、恐らく、一つの手法ではない手法、多様の手法の中で意見を確認していくということだと思うのですけれども、県民投票をそのプロセスの一つに入れれば、一つ、弱点はあるとはいえ、マストの意見を確認できるという利点もあるのかなと思うのですけれども、その辺りに対するお考え・・・。
A 知事
もちろんゼロではないですよね。得られる情報がやはり限られるというのは、前回、記者会見でもお答えしたことですし、今もその気持ちは変わらないのですけれども、かける労力と手間と、得られる情報を比較衡量したときに、有効な方法かということですよね。
Q NHK
最後に一点だけお伺いしますけれども、先ほど県民の意思を確認するときの場面というところとの違いについてなのですけれども、今は県民の意見を見極めるという段階になってくると思うのですけれども、その上で、知事が判断した後に県民の意思を確認する場面が来ると、その中の手法の一つとして・・・。
A 知事
判断についてですね。
Q NHK
判断について、信を問う、意見を確認する場面が出てくる・・・。
A 知事
意思を確認する・・・。
Q NHK
信を問うこととした場合、それが選挙になるとしたら、二者択一になってしまう可能性も・・・。
A 知事
それは判断に対するマルかバツですよね。
Q NHK
その判断に対するものと今の意見を聞く場面での、二者択一では難しいというのと、その判断の場面では二者択一になるのかもしれないというところの認識の違いというのは・・・。
A 知事
判断の場面では二者択一になる・・・。
Q NHK
可能性もあると思うのですけれども。
A 知事
ですので、出した結論について、県民の意思を確認する、その方法については、何度も申し上げているように、正直、今決めているものはないのです。ただ今、意見を、県民の受け止めを探るこの段階においては、このやり方は限定的だと、二者択一という方法では、限定的な情報しか得られない、多様な意見を収集するというところには課題があるねという。申し上げられることは、そこまでです。
Q NHK
判断に対して、恐らく賛否をとることになる可能性はあると思うのですけど、その場面になれば、また少し意見は変わってくるということになると・・・。
A 知事
その場合に住民投票という方法があるかということについては、先ほど少しお話ししましたけれども、方法論として、ないことはないのかもしれませんね。知事の判断、結論に賛成か反対かという、そういったやり方もあるのかもしれませんが、今、いずれにせよ、その意思を確認する方法については、決めていないとしか、申しようがない、ただいずれ決めます。
Q 朝日新聞
県民投票につきまして、二者択一では県民の多様な意見を把握できないということなのですけれども、仮に県議会で修正するということも可能なのですけれども、例えば、選択肢を増やす、例えば二者択一ではなくて、少し選択肢を増やしていって、それで県民投票するということでも、やはり知事は、多様な意見を把握できない・・・。
A 知事
選択肢を増やせば、もちろん得られる情報は増えるでしょうね。
Q 朝日新聞
その場合ですと、今の意見とは少し違う意見・・・。
A 知事
ですので、そこはかける労力やコストなどと、得られる情報の衡量ということになるのでしょうね。
Q 朝日新聞
選択肢が増えることに関しては、衡量の中で県民の意思を把握する手段として、新たに考慮してもいいという考え方に変わる可能性はあるのでしょうか。
A 知事
投票ですから限界がありますよね。アンケートで自由に記述してくださいなどというものとは違いますので、選択肢を無限大に増やすわけにはいかないですよね。そうすると、どちらとも言えないとか、分かりませんけれども、アイデアとしてありそうなものは、条件付き賛成とか、条件付き反対とか、その条件とは何なのかなど、それで得られる投票結果をどう評価したらいいのかというところに帰着しますよね。
Q 朝日新聞
知事としては二者択一というよりも、見極める、把握する方法として、県民投票そのものについて、少し疑問を感じているという理解をしてもよいのでしょうか。二者択一に限らず、県民投票そのもので把握していくということには限界を感じていらっしゃると理解してよいのでしょうか。
A 知事
それは、前回言った通り、限界があると申し上げたところで、ただ、それだけの労力とコストをかけても、やる意味があると思う人もいるかもしれませんよね。私は、今の段階、フェーズは、県民の受け止めを見極める、探るという段階で、条例案を提案された皆さんも知事の判断に資するためと仰っているのです。それは、もちろんゼロではないけれども、得られるものは少ないよねというのが私の気持ちです。
Q 読売新聞
知事意見の中で、先ほどの質疑でもあったのですけれども、知事意見の中でも条件付きの賛否という声が、県民から寄せられているという文言があるのですけれども、その条件というのは、例えば避難道整備等だと思うのですけれども、代表的なものとしてはどのようなものが・・・。
A 知事
今言った避難路整備や、避難所の整備など、あるいは経済的メリットがありやなしやとか、そういったものが条件になっているのではないでしょうか。
Q 読売新聞
今3つ例示されましたけれども、大きなものはこの3つが・・・。
A 知事
分かりません。他にもまだ私が今、瞬間で思い浮かばないものがあるのかもしれません。
Q 新潟日報
県民投票条例案に関してなのですが、今後、議会によっては実施されることもあり得ると思うのですけれど、先ほどから得られるものは少ないということでしたけれども、県民投票の結果というものがあったとしても、知事の判断には影響を与えない・・・。
A 知事
条例には尊重すると書いてありますから、尊重していかなければいけない。
Q 新潟日報
ただ、知事として得られるものは少ないという考えには変わりがない・・・。
A 知事
投票から得られるものがですね。投票の結果については尊重と、ただその投票の結果をどう評価したらいいのかというところは、本質的な問題としては残りますけれども、先ほど、選択肢を広げていったら、これはどういったように捉えたらいいのかとなっていきかねないのです。
Q 朝日新聞
原発について、県民からの声が大勢寄せられるということでしたけれども、大勢というのはどれほどの規模感なのでしょうか。
A 知事
すべて、原文が来るわけではなく、整理されてきますので、月に1回程度、まとめて報告が来ているでしょうか、必ず数件はありますよね。
Q 朝日新聞
知事が任期2期目ですけれども、1期目から2期目にかけて増えてきた・・・。
A 知事
原文を全部見ていないので恐縮なのですが、変わらないという感じです。ものすごく多く書き込みのある便りもあれば、反対とか、それだけのこともあるので、何とも言えないのですけれども、コンスタントに声は来ているという感じでしょうか。
Q 朝日新聞
月に何件来ている・・・。
A 知事
しかも県民だけではないのです。住所不詳のケースもありますし、明らかに別の県からのものもありますし、何とも言えないところはあります。
Q 朝日新聞
全体の件数の報告があった上で、さらに精査されたものがお手元に届くという・・・。
A 知事
文章で長いものは、全部もらっているのではないでしょうか。
Q 朝日新聞
知事が仰った大勢というのは、月に100通とか・・・。
A 知事
大勢といいますか、沢山いただいているという・・・。
Q 朝日新聞
分量、意見の量・・・。
A 知事
意見の量は、反対という二文字くらいのものもあれば、一生懸命ご意見を書き込まれたようなものもありますし、随時寄せられていますということを申し上げています。
Q 朝日新聞
県民の判断になるように、県民の意見を公表するお考えは・・・。
A 知事
今でも便りは公表しているのではないでしょうか。仕組みは分かりませんけれども。
Q 新潟日報
県民投票の関係で、マルバツだと0ではないけれども、得られるものは少ないということで、仮に県民投票が行われた場合、投票率が仮にとても高かった場合でも、その場合、マルが非常に多くて、バツが少ないなどでも、やはりマルでも、濃淡、積極的にマルや消極的なマルもあるので、得られるものが少ないという捉え方でよろしいでしょうか。投票率の高い低い関係なく・・・。
A 知事
投票率という議論は、今初めて出ましたけれども・・・。
Q 新潟日報
仮に投票総数が多いと、それだけマルの数が多ければ、マルの意見が多いというのは何となく分かると思うのですけれども・・・。
A 知事
もちろんその通りです。投票率が高くて、マルが多ければ、マルの人の割合が多いということになります。
Q 新潟日報
そこからでも得られる情報というのは限られる・・・。
A 知事
得られる情報と私が言っているのは、例えば、条件付き賛成や、条件付き反対という人たち、それから、強く反対する人たち、どちらかといえばというような、そういったグラデーションがありますよねと。前回も誰かがご質問で、声なき声と仰ったような気がしますけれども、そういったものを拾って、何が一体、悩みごとであり、不安なのだろうというところを探ることが、行政や政治の課題ではないかと先ほど申し上げました。そういったものを集めて、見極めていくということが、まさに県民の受け止めを見極めるということになるのだと思っています。
Q 新潟日報
県民投票条例で、例えば知事が二者択一の方向に消極的とか、否定的とか、例えばそういった評価の部分は、我々がするわけで、これについては、知事、コメントする立場ではないという話がありましたけれども、この評価が知事の思いと間違ったところに、逆の方向に行かないためにも、この評価についてのコメントといいますか、あり方について、知事がどう思っているのかについては、確認したいところであるのですが、それを言及されないというのは・・・。
A 知事
人の評価は人の評価でしかないので・・・。
Q 新潟日報
真逆の評価ということは、今までは・・・。
A 知事
それはまさに出した意見、付けた意見を読んでいただければ、住民投票というものの持つ特徴なり、何といいますか、効果のようなものは、私の捉え方は伝わっていると思います。
Q 新潟日報
今、質問が多く出ましたけれども、やはりその評価の部分はとても関心が高くて、知事がいろいろな条件はあるにせよ、実際、最終的にどう思って、どう評価されているのかというのは、その意見の中でポイントだと思うのですが・・・。
A 知事
それは随時お答えしましたよ。
Q 新潟日報
それで十分・・・。
A 知事
例えば、元々、住民投票制度自体、私は否定をしていないし、間接民主制を補完する重要な民主主義の手段だと思っています。ただこの局面で、私が県民の意見を見極めていこうとする段階での、効果というものには限界がありますね。
Q 新潟日報
今のようなお話をまた県議会、臨時会でも・・・。
A 知事
県議会でのご質問は、ご質問としてお答えしていきます。
(主要地方道 松代高柳線(柏崎市高柳町門出地内)における道路崩落について)
Q 新潟日報(代表幹事)
柏崎市高柳町の県道崩落について伺います。3月26日の発生から(4月)9日で2週間となります。現地は通行止めが続いていますが、現状と復旧の見通しについてお願いします。
A 知事
4月2日、先週の水曜日に専門家による現地調査もお願いをして、実施しています。そのアドバイスをいただきまして、現在、昨日から斜面の上部の水を排水、排除する工事を行っていると聞いています。そして明日から、ボーリング調査を始めるということで、こうしたボーリングによる地質調査の結果を待って、復旧方法を検討し、その後、工事に着手ということで、現状では復旧見通し、まだ立っていないのですけれども、できるだけ早期復旧に努めたいと思っています。進捗状況については、非常に心配されている地域の住民の皆さんに、丁寧に説明するように心がけたいと思いますし、また県のホームページなどでも、情報を公表したいと思っています。
Q 新潟日報(代表幹事)
雪解けの水の関係で、かなり難しいといいますか、なかなか進まない感じも・・・。
A 知事
私も専門家ではないので、詳しくは分からないのですが、どういった形で復旧させていくのか、かなり検討が要るようです。
Q 新潟日報
(4月)6日のトランプ政権による関税措置について伺います。今日の午後にも相互関税の第二弾が発動されるとのことなのですけれども、改めて県内としては、農林水産物などを含めて、県内の影響がどれほど出るとみているのか知事の考えがあればお願いいたします。
A 知事
影響は間違いなく出ると思いますが、どの程度出るのか、どのような形で出てくるのか、そこは本当にしっかり見ていく必要があると思っています。国の方もいろいろな相談窓口を設けて、県内にも数十ヶ所ほど相談窓口をつくるというように聞いていますし、県としても、どのような影響が出てくるのか、しっかり情報を集めていきたいと思います。
Q 新潟日報
他県では関係機関を交えた対策会議を・・・。
A 知事
必要があれば、そういったことも考えたいと思います。
Q 新潟日報
いつ頃開催されるかは、またこれから・・・。
A 知事
そういった会議体のようなものが必要なのかどうかも含めて、考えていきたいと思います。
Q 新潟日報
県としても相談窓口を(4月)4日に設置されていると思うのですけれども、改めて、今後その資金繰りの悪化が懸念される企業に対する支援策など、考えているものがありますでしょうか。
A 知事
具体的に私のところまでその相談は来ていないのですけれども、当然、本当に影響が出て、輸出が止まるなど、そのことによって経営上に大きな打撃があるような企業が出てくれば、そういったことが見込まれる状況であれば、そうしたセーフティーネット的な融資など、今でも必要なものはありますけれども、考えていかなければならないと思います。
Q 新潟日報
県の企業局が管理する県営高田発電所の近くで、(4月)6日に土砂崩れが起きたことについて伺います。今回、発電所に水を送る水管が破断したとのことだったのですけれども、これまでの調査で、その原因について分かっていることなどがあれば、お願いいたします。
A 知事
それは担当部局に確認してもらいたいと思います。私が報告を受けているのは、原因は今、究明中であって、恐らくは土砂崩れが先にあって、破断したのだろうという推測でしかまだ聞いていません。いずれにしても、原因究明を急いでいると思いますので、その上で対処方針は、どういった形でこれから復旧していくかということを考えなくてはいけないので、最新の状況については部局に確認していただきたいと思います。
Q 新潟日報
復旧までどれくらいかかるかという見通しは・・・。
A 知事
まだ見通しは立っていないと思いますね。まず原因を見極めるところからだと思います。
※文中の( )内については、広報広聴課で加筆したものです。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ
知事政策局 広報広聴課
企画調整係
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎4階
Tel:025-280-5013Fax:025-283-2274メールでのお問い合わせはこちら
- ごうぎんエナジー株式会社によるPPA事業の契約締結について 〔04/16 山陰合同銀行〕
- フィルム型ペロブスカイト太陽電池の小規模実証研究開始について 〔04/16 沖縄電力〕
- 合成燃料の事業会社 米国Infinium社への出資参画 〔04/16 三井物産〕
- インドネシア商用石炭火力発電所においてASEAN初となるグリーンアンモニアでの燃焼実証に成功 〔04/16 IHI〕
- 国内の新規着工現場から使用電力を100%グリーン電力化 〔04/16 清水建設〕
- リンナイ(株)製 浴室暖房乾燥機をご使用のお客さまへ 〔04/16 北海道瓦斯〕
- フィルム型ペロブスカイト太陽電池の小規模実証研究開始について 〔04/16 沖縄電力〕
- エネファーム導入による J-クレジット創出プロジェクトの開始について 〔04/16 静岡ガス〕
- 原子力プラントの廃止措置工事に係る地元企業等との共同研究~2025年度募集~ 〔04/16 関西電力〕
- 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 〔04/16 東京電力ホールディングス〕
情報提供:JPubb