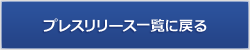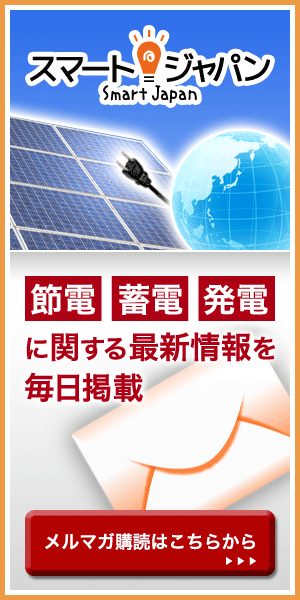プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
建築物省エネ法
建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、誘導措置は平成28年4月1日、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。また、令和7年4月1日の法改正により、原則、全ての住宅・非住宅建築物が省エネ基準適合義務の対象となりました。
1.建築物省エネ法の背景
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物(注:令和7年4月1日以降は「原則、全ての住宅・非住宅建築物」)のエネルギー消費性能基準への適合義務、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。
2.建築物省エネ法の概要
省エネ適合性判定
原則、全ての住宅・非住宅建築物について、新築・増改築を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務が課され、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
また、令和7年4月1日以降は住宅を仕様基準又は誘導仕様基準で評価した場合に限り、省エネ適合性判定を省略し、建築確認申請の中で省エネ基準適合を確認することもできることとなりました。(建築確認申請の手数料に省エネ審査に係る手数料が別途加算されます。)
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(外部サイトへリンク)
茨城県内の地域の区分(4地域~6(7)地域)(PDF:75KB)
※令和3年4月1日以降の新築は新地域区分のみ適用されます(認定も同様)。
(参考)省エネ適合性判定の審査の特例について
建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物は省エネ適合性判定が審査の特例により不要とされます。
なお、省エネ基準適合義務はかかりますのでご注意ください。
(参考)省エネ基準適合義務の適用除外について
以下の建築物・建築行為については省エネ基準適合義務の適用除外(省エネ適合性判定も不要)となります。
適用除外の判断については、必ず提出先機関へもご相談ください。
①10㎡以下の新築・増改築
②居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
③歴史的建造物、文化財等
④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
なお、省エネ基準に係る施工状況の検査については、建築基準法の完了検査の際に行う仕組みになっています。
省エネ基準適合義務対象建築物に係る 完了検査の手引き(外部サイトへリンク)
【完了検査申請時の添付様式(県様式)】
省エネ基準工事監理報告書(住宅・仕様基準)(エクセル:18KB)
省エネ基準工事監理報告書(住宅・性能基準)(エクセル:22KB)
省エネ基準工事監理報告書(非住宅・モデル建物法)(エクセル:19KB)
省エネ基準工事監理報告書(非住宅・モデル建物法(小規模版))(エクセル:19KB)
省エネ基準工事監理報告書(非住宅・標準入力法)(エクセル:21KB)
軽微変更説明書(住宅・仕様基準)(ワード:31KB)
軽微変更説明書(住宅・性能基準)(ワード:26KB)
軽微変更説明書(非住宅)(ワード:31KB)
軽微変更該当証明申請書(省エネ適合性判定)(ワード:26KB)
省エネ性能向上計画認定
新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができ、認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はおこなえません。)
【完了検査申請時の添付様式(県様式)】
軽微変更該当証明申請書(省エネ性能向上計画認定)(ワード:26KB)
取下届
建築物省エネ法等により知事に提出した計画書、通知書、申請書を取り下げようとする場合は「申請書等取下届」を提出してください。
(参考)建築物省エネ法の手続き一覧
| 対象建築行為 | 申請者 | 提出先等 | 適用基準 |
|---|---|---|---|---|
省エネ適合性判定 | 原則、全ての住宅・非住宅建築物の新築・増改築 | 建築主 | 所管行政庁 又は 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定 | 省エネ基準 |
省エネ性能向上計画認定 | 新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修 用途・規模限定なし | 建築主等 | 所管行政庁が認定 | 省エネ誘導基準(省エネ基準より厳しい基準) |
3.提出先
省エネ適合性判定の提出先
以下(1)又は(2)の提出先に提出ください。(対象建築物の規模・用途により提出先が異なります。)
なお、省エネ適合性判定は行政庁以外でも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることが可能です。また、市特定行政庁(水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市)の管轄においては、各市役所担当課が提出先になります。
| 提出先 | 対象建築物 | |
| (1) | 土木部都市局建築指導課建築担当 〒310-8555 水戸市笠原町978-6(県庁舎20階) 電話番号:029-301-4727 | 公立学校、工場及び倉庫以外の建築物であって、「5以上の階数を有するもの」又は「延べ面積が2,000平方メートル以上のもの」 |
| (2) | 各県民センター等 | 上記に掲げる以外の建築物 |
省エネ性能向上計画認定の申請先
土木部都市局建築指導課建築担当へ申請ください。
なお、水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市においては、各市役所担当課が提出先になります。
4.手数料
省エネ適合性判定の手数料
省エネ適合性判定及び軽微な変更に関する証明書の交付の手数料は、茨城県手数料徴収条例に定められています。なお、省エネ適合性判定を省略し、建築確認申請の中で省エネ基準適合を確認する場合(住宅を仕様基準又は誘導仕様基準で評価した場合に限る)の省エネ審査に係る手数料の加算額は建築確認申請の手数料を参照してください。
申請手数料一覧
※手数料は茨城県収入証紙又はキャッシュレス(ペイジー又はクレジットカード)により納付してください。登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を依頼する場合は、各機関にお問合せください。
省エネ性能向上計画認定の手数料
省エネ性能向上計画認定の手数料は、茨城県手数料徴収条例に定められています。
申請手数料一覧
※手数料は茨城県収入証紙又はキャッシュレス(ペイジー又はクレジットカード)により納付してください。
※複数建築物の認定(熱源機器の共有等)については、各建築物毎に申請手数料を算定した合計額となります。
※省エネ性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明書の申請にあっては、手数料はかかりません。
5.関連ホームページについて
- 国土交通省HP(建築物省エネ法関連)(外部サイトへリンク)
(主な内容)
関係法令(法律、政令、省令、告示)、様式等
登録建築物エネルギー消費性能判定機関情報 - 国立研究開発法人建築研究所HP(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報)(外部サイトへリンク)
(主な内容)
一次エネルギー消費量計算プログラム
外皮性能評価プログラム
非住宅建築物のモデル建物法評価支援ツール
計算プログラムの解説
基準の解説及び補足資料 - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP(外部サイトへリンク)
(主な内容)
省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索 - 省エネサポートセンター(一般財団法人建築環境・省エネルギー機構)(外部サイトへリンク)
(主な内容)
制度全般・省エネ基準に関する質問 - 建築物省エネアシストセンター(一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会)(外部サイトへリンク)
(主な内容)
設計・工事監理に関する相談
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課建築
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4727
FAX番号:029-301-4739
お問い合わせフォーム
- Kanadevia Inova、米国でごみ焼却発電プラント関連企業を買収 〔04/04 カナデビア〕
- 水力発電所フォトコンテストについて 〔04/04 山口県庁〕
- 太陽光発電所の共同事業における第1号案件について 〔04/04 石油資源開発〕
- 循環型再生エネルギーシステムのコア部品の試験を国際宇宙ステーションで実施 ~米国の宇宙関連企業・機関とのパートナーシップを担う部門をアメリカン・ホンダモーター内に新設~ 〔04/04 本田技研工業〕
- 再エネ・蓄電池の価値最大化をサポートする電力販売支援サービスの提供開始 〔04/04 ユーラスエナジーホールディングス〕
- 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 〔04/06 東京電力ホールディングス〕
- 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 〔04/05 東京電力ホールディングス〕
- 福島第一原子力発電所の状況について(日報) 〔04/04 東京電力ホールディングス〕
- 再エネ・蓄電池の価値最大化をサポートする電力販売支援サービスの提供開始 〔04/04 ユーラスエナジーホールディングス〕
- レジルが東北電力の「くらしサービス」において運営支援を開始 〜「REZIL BPaaS」を成長させたノウハウで、新規事業の強化を後押し〜 〔04/04 レジル〕
情報提供:JPubb