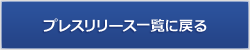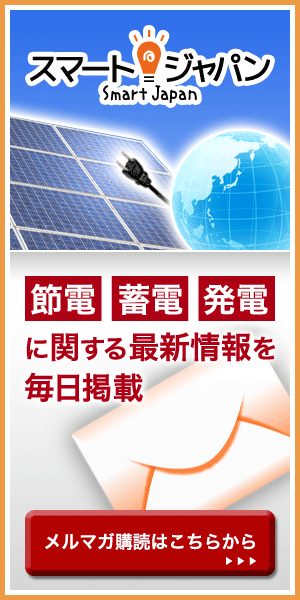プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年3月14日) - キーワード:文部科学省の「地方創生2.0」に向けた取組、石破総理による自民党議員への商品券配布の報道、宮崎産業経営大学で働いていた元助教の地位確認を求める裁判、日本原子力研究開発機構が世界で初めてウランを用いた蓄電池を開発、中教審委員の任命に関する意見と国立大学の授業料の在り方、公立高校の入学者選抜の実施方法の在り方、高等教育の修学支援制度の拡充に関する周知
あべ俊子文部科学大臣記者会見録(令和7年3月14日)
令和7年3月14日(金曜日)
教育、科学技術・学術、その他
キーワード
文部科学省の「地方創生2.0」に向けた取組、石破総理による自民党議員への商品券配布の報道、宮崎産業経営大学で働いていた元助教の地位確認を求める裁判、日本原子力研究開発機構が世界で初めてウランを用いた蓄電池を開発、中教審委員の任命に関する意見と国立大学の授業料の在り方、公立高校の入学者選抜の実施方法の在り方、高等教育の修学支援制度の拡充に関する周知
あべ俊子文部科学大臣記者会見映像版
令和7年3月14日(金曜日)に行われた、あべ俊子文部科学大臣の記者会見の映像です。
令和7年3月14日あべ俊子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
あべ俊子文部科学大臣記者会見テキスト版
記者)
今週11日に石破総理が福島を視察し、地方創生イノベーション構想の関係省庁会議を立ち上げる旨を発表するなど、石破政権の地方創生2.0の取組が今後加速されていくと思われます。改めて、大臣の意気込みについて教えていただけますでしょうか。
大臣)
総理も仰っているとおり、「地域づくりは人づくり」、人材育成こそ全てでございまして、石破内閣が掲げる地方創生2.0に向けまして、文部科学省に期待される役割は大変大きいものであるというふうに受け止めているところでございます。また、先月2月27日に開催されました新しい資本主義実現会議におきまして、文部科学大臣と経済産業大臣を中心に産業人材育成のためのプランを具体化することについて総理指示があったことを踏まえまして、現在、経済産業省とも連携しながら産業人材育成について地方創生の観点も重視をしながら、その必要な分野も含めて検討しているところでございます。4月上旬にも、この検討の背景や状況等について産業界との連携に関心のある自治体等と共有、意見交換する機会を設けることを考えているところでございまして、さらに議論を深めていきたいというふうに考えています。以上です。
記者)
昨日、石破総理が1期目の衆議院議員の方々に対して商品券を渡していたということが明らかになりました。このことについて大臣の受け止めと、また総理から大臣自身、商品券を受け取ったような経験があるのかどうか、お聞かせください。
大臣)
昨日、総理が説明されたことは報道で承知をしているところでございまして、それ以上の事実関係の詳細は承知しておりませんので、この場でコメントは差し控えさせていただきますが、私自身のことで言えば個人的なことをこの場で申し上げるのは控えさせていただきますが、私自身のことは控えさせていただきます。
記者)
宮崎産業経営大学の助教をしてきた女性が職場結婚をしたら雇い止めにあったなどとして、大学法人と理事長兼学長に国民訴訟を起こしたというニュースがありました。大学を所管する大臣としての受け止めを教えてください。また、所轄庁として事実確認を含めて指導・調査などをする御予定があるのか教えてください。
大臣)
御指摘の件につきましては、宮崎産業経営大学を設置する学校法人大淀学園から、文部科学省の担当課に対して状況の報告があったと聞いておりますが、本件は、訴訟が提起された事案でございますのでコメントすることは差し控えさせていただきます。また、繰り返しになりますが、まずは訴訟が提起された事案でございますのでまずは状況を注視したいというふうに考えております。
記者)
昨日、日本原子力研究開発機構がこれまで厄介者とされていた劣化ウランを使うことができる新しい蓄電池を開発しました。これについての大臣の受け止めと、今後のこうした基礎的な研究開発への支援について教えてください。
大臣)
原子力機構におきまして、原子力発電用の燃料製造時に副産物として発生する劣化ウランを利用した蓄電池の開発に世界で初めて成功したと承知をしているところでございます。今年1月に原子力機構を視察した際に、この本研究が実用化されれば、太陽光の発電また風力発電等の変動調整に活用できると伺って大変深い関心を持っていたところでございまして、今回の成果発表を聞きまして大変嬉しく思いました。また、原子力機構において今回発表された成果の実用化に向けまして、引き続き技術課題に果敢にチャレンジしていただくことを御期待申し上げる次第でございまして、まず文部科学省としては引き続き幅広い原子力科学技術の取組をしっかりと推進してまいります。以上です。
記者)
先日、中央教育審議会の委員が任命されましたが、この件について島根県知事が記者会見の中で文科大臣を国賊という言葉で非難されていました。このことについての大臣の受け止めと、またその非難の理由というのが国立大学の授業料について値上げを主張されている方が委員に含まれていたからということのようなのですけれども、島根県知事は自身の考えとして国立大学の値上げが実現すれば少子化対策の効果がなくなるとも主張されていました。改めてにはなりますが、国立大学の授業料のあり方について大臣の現時点での見解を合わせてお聞かせいただければと思います。
大臣)
強いお言葉でございました。個別の御意見に対して、この場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、第13期の中央教育審議会の委員につきましては、今後の教育政策の在り方を審議していくために、幅広い意見を取り入れる体制としたところでございます。また、伊藤委員をはじめ、国公私立、また都市部・地方と様々な立場の大学の学長に幅広く御参画いただいておりまして、今回の委員構成の一つの特徴だというふうに考えています。審議会全体のバランスを総合的に勘案しまして人選を行いましたので、個別の委員の選任理由についてはお答えを差し控えさせていただきますが、委員の皆様にはそれぞれの専門性と知見を生かして活発に御審議いただくことを期待しております。以上です。
もう一つ、非難にあたりましてのことでございますが、国立大学の授業料に関しまして国が示す標準額の設定に当たりましては、国立大学の役割を踏まえつつ、私立の大学の授業料水準等や社会経済の情勢、また家計負担の状況も踏まえまして総合的に勘案する必要があるというふうに考えています。このため、今後、「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」におきましては、「法人、国、ステークホルダー間での教育研究コストの適切な負担」につきまして議論を深めていただきたいと考えているところでございまして、国立大学の授業料の在り方については、この議論の状況等も踏まえつつ、丁寧に検討してまいります。以上です。
記者)
公立高校入試改革についてお尋ねします。河野太郎衆議院議員がSNS上で公立高校入試の単願制について、生徒の学校選択に不公平、非効率な状況を生み出していると指摘していて、その解決策として「受け入れ保留アルゴリズム」方式などのデジタルシステムを導入していくべきと主張しています。あべ大臣も単願制の改革を進めると訴えたとありますが、本件について今後の改革の方向性、今後の改革の方向性について教えてください。
大臣)
今、アルゴリズムもおっしゃいましたか。
記者)
そうです。
大臣)
分かりました。公立高校の入学者選抜の実施方法に関しましては、出願方法やデジタルシステム導入の可否を含めまして、実施者である各都道府県教育委員会等が決定するものでございますが、その具体的な実施方法等については様々な御意見があるものと承知をしておりまして、私どもとしても課題意識を持っているところではございます。文部科学省におきましては、受験機会の複数化、また選抜方法の多様化などへの配慮に加え、デジタル技術の活用など入学志願者の利便性の向上、また実施者及び教職員の負担軽減に資する取組については、実情に応じてさらに推進していただくよう依頼をしているところでございます。一方で、いわゆる高校無償化をめぐる議論の中におきまして、高校入試を含めた公立高校のあり方が改めて問われているということもございまして、今後、文部科学省としても考えていきたいというふうに思います。また、お尋ねの「受け入れ保留アルゴリズム」方式については、詳細を把握しておりませんが、この入学者選抜におきましては生徒の個性を多面的に捉えることなども重要でございまして、例えば点数のみにより進学先が決定される場合には課題も考えられます。このことも踏まえた検討が必要になるのだというふうに考えているところです。以上です。
記者)
この4月から多子世帯の大学無償化が始まると思います。修学支援新制度が始まってから数年経ちますが、度々周知不足ということは指摘されていると思います。今回の対象拡大に関してどのように周知、広報を行っていく御予定か教えてください。
大臣)
高等教育の修学支援新制度について、必要な方々に支援を届けながら御活用いただくためには、また今回の制度改正によりまして支援対象者数が大幅に増加することも踏まえますと積極的な情報発信、関係者の分かりやすい説明が重要だというふうに考えています。文部科学省としては、今回の制度改正の内容を含めまして昨年1月から学生等や進学を控えた高校生に向けましてSNS、動画配信、TV放送、インターネット広告等、様々な広報媒体を活用して制度内容を分かりやすく発信はしてまいりました。また、今後、支援対象になり得る新高校3年生に対しては全員を対象にリーフレットを配布して周知をするとともに、家庭の経済状況により早い段階で大学等への進学を断念してしまう可能性もある中学3年生に対しても周知資料を配布するなど積極的に案内してきたところでございまして、引き続き丁寧な周知を行ってまいりたいというふうに思います。
(了)
- ページの先頭に戻る
お問合せ先
大臣官房総務課広報室
- インドにおけるグリーンアンモニア製造プロジェクトへの出資検討に関する覚書を締結 ~日本初のグリーンアンモニア輸入に向けて~ 〔03/25 商船三井〕
- 大磯町の17施設に再生可能エネルギー100%電力を供給~大磯町の公共施設等におけるCO2排出量を約73%、年間約1,500トン削減~ 〔03/24 コスモエネルギーホールディングス〕
- ペロブスカイト太陽電池の発電効率を向上させる電子輸送層の成膜用インクを開発 ~従来型のインクより約1.5倍の高発電効率を実現~ 〔03/24 三菱マテリアル〕
- 令和6年度第3回洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会を開催〜昨今の基地港湾を取り巻く課題への対応案をとりまとめ〜 〔03/24 国土交通省〕
- 県有施設にPPA方式で太陽光発電設備を導入しました 〔03/24 栃木県庁〕
- 2025年4月人事異動について 〔03/25 東北電力〕
- 法人のお客さま向け「中電カーボンオフセット天然ガス」の販売開始~大同特殊鋼(株)知多第2工場において天然ガス・電気のCO2フリー化を実現~ 〔03/25 中部電力〕
- 2025年3月度 定例記者会見 林社長挨拶 〔03/24 中部電力〕
- 2026年度採用計画 〔03/24 中部電力〕
- 災害時の相互協力に関する協定の締結 〔03/24 中部電力〕
情報提供:JPubb