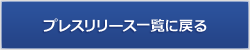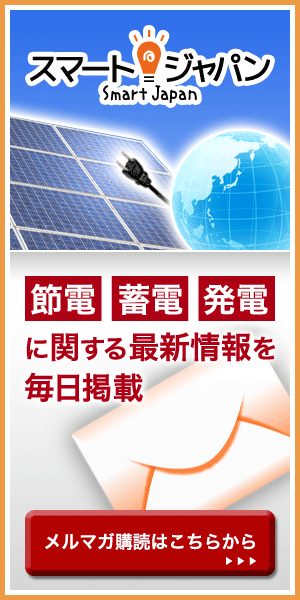プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
≫ 2025-02-04 00:00:00 更新
災害現場における水素エネルギーの普及に向けて厳冬期の避難所を想定した燃料電池発電機の実証実験を実施[帝人]
2025年2月4日
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所
帝 人 株 式 会 社
災害現場における水素エネルギーの普及に向けて厳冬期の避難所を想定した燃料電池発電機の実証実験を実施[帝人]
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所(所在地:東京都渋谷区、所長:富田 博樹、以下「災害救護研究所」)と帝人株式会社(本社:大阪市北区、社長:内川 哲茂、以下「帝人」)は、このたび、北海道北見市にて、厳冬期の災害における避難所での使用を想定した燃料電池発電機の有効性を確認する実証実験を国内で初めて実施しました。
実証実験には、株式会社しかおい水素ファーム(本社:北海道河東郡鹿追町、社長:末長 純也、以下「しかおい水素ファーム」)が家畜のふん尿由来のバイオガスから製造した水素を使用しました。
1.背 景
(1)日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授(同大学災害対策教育センター長)は、厳冬期において健康な避難所生活に必要な要素として「T(トイレ)、K(キッチン)、B(ベッド)+W(ウォーム・暖房)」を満たすことを提言しています。これらの要素を確保するためには、長時間の停電に備えた非常用電源の確保が重要です。特に、厳冬期における災害時の避難所においては、低温が原因で命を落とすリスクもあり、暖を取ることができる環境の整備が必要です。
(2)現在、非常用電源にはさまざまな発電機が利用されていますが、ガソリン発電機などは、使用時の騒音や臭いの問題、また、稼働中に排出される一酸化炭素による中毒のリスクが存在しています。
(3)これらの問題解決やリスク回避に向けて、日本赤十字看護大学の附属機関で赤十字の災害救援技術の研究開発を行う災害救護研究所と、燃料電池発電機の社会実装を目指す帝人は、寒冷地の避難所における燃料電池発電機の有効性を確認するための実証実験を、日本赤十字北海道看護大学が主催する厳冬期災害演習の中で行いました。本演習には自治体職員や医療関係者など約160名が参加しました。
2.厳冬期災害演習における燃料電池発電機の実証実験について
(1)災害救護研究所に所属する根本昌宏教授の監修のもと、実際の災害発生後の避難所を模倣した環境を再現のうえ、帝人が開発した燃料電池発電機である燃料電池ユニットと、同ユニットに水素を供給する圧力容器ユニットを使用しました。圧力容器ユニットには、帝人エンジニアリング株式会社が展開する複合材料容器「ウルトレッサ」を搭載しています。
(2)実証実験を通じて、厳冬期の避難所内でも燃料電池発電機が安全・安定に稼働し、各種電気機器への給電を継続することや、電源が必要とされる場所での燃料電池発電機の設置や運用の作業、稼働に伴う運転音が、避難所での生活の妨げとならないかどうかを検証しました。
【実証実験の概要】
実施時期:2025年1月18日~2025年1月19日
実施場所:日本赤十字北海道看護大学(北海道北見市)
使用環境:[体育館内の気温]1~3度 / [エントランスの気温]5~10度
稼働機器:[ 体 育 館 内 ]照明機器、防災用トイレ、暖房設備(ジェットヒーター)
[エントランス]電気ポット、電子レンジ
3.実証実験の結果
(1)実証実験中、燃料電池発電機は安定して電気機器への給電を継続できました。照明機器、防災用トイレ、ジェットヒーターの稼働テストを実施し、問題なく稼働できることを確認しました。一部の電気ポットや電子レンジの給電にも使用し、演習参加者が温かい食事を取ることに寄与したことから、低体温症を予防する環境の整備にも貢献できました。また、厳しい環境での運転を通じて、発電機システムのさらなる安全性・信頼性向上に向けた課題についても確認することができました。
(2)燃料電池発電機の運転音は、電気ポットへの給電場所における測定値で60デシベルから65デシベルでした。演習参加者からは音による不快感は少ないとの声がありましたが、特に避難所内での就寝時など、静粛な環境が求められるシーンでは改善の必要性があることが災害救護研究所の研究員により指摘されました。
(3)今回の実証実験を通じて、厳冬期の避難所においても、一定条件下では燃料電池発電機が有効に活用できることを確認しました。
以上
【ご参考:しかおい水素ファームについて】
しかおい水素ファームは、国内で唯一、家畜のふん尿を発酵させたバイオガスから水素を製造する企業です。水素の製造工程で一緒に生み出される二酸化炭素は、家畜のエサである牧草の光合成を通じて大気から吸収するため、カーボンニュートラルに寄与します。
【 本件に関するお問合せ先 】
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所 TEL:(03)3409-0684
帝人株式会社 コーポレートコミュニケーション部 TEL:(03)3506-4055
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所
帝 人 株 式 会 社
災害現場における水素エネルギーの普及に向けて厳冬期の避難所を想定した燃料電池発電機の実証実験を実施[帝人]
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所(所在地:東京都渋谷区、所長:富田 博樹、以下「災害救護研究所」)と帝人株式会社(本社:大阪市北区、社長:内川 哲茂、以下「帝人」)は、このたび、北海道北見市にて、厳冬期の災害における避難所での使用を想定した燃料電池発電機の有効性を確認する実証実験を国内で初めて実施しました。
実証実験には、株式会社しかおい水素ファーム(本社:北海道河東郡鹿追町、社長:末長 純也、以下「しかおい水素ファーム」)が家畜のふん尿由来のバイオガスから製造した水素を使用しました。
1.背 景
(1)日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授(同大学災害対策教育センター長)は、厳冬期において健康な避難所生活に必要な要素として「T(トイレ)、K(キッチン)、B(ベッド)+W(ウォーム・暖房)」を満たすことを提言しています。これらの要素を確保するためには、長時間の停電に備えた非常用電源の確保が重要です。特に、厳冬期における災害時の避難所においては、低温が原因で命を落とすリスクもあり、暖を取ることができる環境の整備が必要です。
(2)現在、非常用電源にはさまざまな発電機が利用されていますが、ガソリン発電機などは、使用時の騒音や臭いの問題、また、稼働中に排出される一酸化炭素による中毒のリスクが存在しています。
(3)これらの問題解決やリスク回避に向けて、日本赤十字看護大学の附属機関で赤十字の災害救援技術の研究開発を行う災害救護研究所と、燃料電池発電機の社会実装を目指す帝人は、寒冷地の避難所における燃料電池発電機の有効性を確認するための実証実験を、日本赤十字北海道看護大学が主催する厳冬期災害演習の中で行いました。本演習には自治体職員や医療関係者など約160名が参加しました。
2.厳冬期災害演習における燃料電池発電機の実証実験について
(1)災害救護研究所に所属する根本昌宏教授の監修のもと、実際の災害発生後の避難所を模倣した環境を再現のうえ、帝人が開発した燃料電池発電機である燃料電池ユニットと、同ユニットに水素を供給する圧力容器ユニットを使用しました。圧力容器ユニットには、帝人エンジニアリング株式会社が展開する複合材料容器「ウルトレッサ」を搭載しています。
(2)実証実験を通じて、厳冬期の避難所内でも燃料電池発電機が安全・安定に稼働し、各種電気機器への給電を継続することや、電源が必要とされる場所での燃料電池発電機の設置や運用の作業、稼働に伴う運転音が、避難所での生活の妨げとならないかどうかを検証しました。
【実証実験の概要】
実施時期:2025年1月18日~2025年1月19日
実施場所:日本赤十字北海道看護大学(北海道北見市)
使用環境:[体育館内の気温]1~3度 / [エントランスの気温]5~10度
稼働機器:[ 体 育 館 内 ]照明機器、防災用トイレ、暖房設備(ジェットヒーター)
[エントランス]電気ポット、電子レンジ
3.実証実験の結果
(1)実証実験中、燃料電池発電機は安定して電気機器への給電を継続できました。照明機器、防災用トイレ、ジェットヒーターの稼働テストを実施し、問題なく稼働できることを確認しました。一部の電気ポットや電子レンジの給電にも使用し、演習参加者が温かい食事を取ることに寄与したことから、低体温症を予防する環境の整備にも貢献できました。また、厳しい環境での運転を通じて、発電機システムのさらなる安全性・信頼性向上に向けた課題についても確認することができました。
(2)燃料電池発電機の運転音は、電気ポットへの給電場所における測定値で60デシベルから65デシベルでした。演習参加者からは音による不快感は少ないとの声がありましたが、特に避難所内での就寝時など、静粛な環境が求められるシーンでは改善の必要性があることが災害救護研究所の研究員により指摘されました。
(3)今回の実証実験を通じて、厳冬期の避難所においても、一定条件下では燃料電池発電機が有効に活用できることを確認しました。
以上
【ご参考:しかおい水素ファームについて】
しかおい水素ファームは、国内で唯一、家畜のふん尿を発酵させたバイオガスから水素を製造する企業です。水素の製造工程で一緒に生み出される二酸化炭素は、家畜のエサである牧草の光合成を通じて大気から吸収するため、カーボンニュートラルに寄与します。
【 本件に関するお問合せ先 】
日本赤十字看護大学附属災害救護研究所 TEL:(03)3409-0684
帝人株式会社 コーポレートコミュニケーション部 TEL:(03)3506-4055
再生可能エネルギー等に関するプレスリリース
- 自治体のカーボンニュートラル実現を支援するJ-クレジット創出サービスの拡充について~家庭用太陽光発電システムを対象に追加~ 〔02/10 東邦瓦斯〕
- 米国Enphase Energy Inc.との日本市場における戦略的業務提携について 〔02/10 伊藤忠商事〕
- WIND EXPO【春】~第15回 [国際] 風力発電展~出展のお知らせ 〔02/10 ユーラスエナジーホールディングス〕
- 陸上風力発電所のO&Mサービスを提供開始 ~国内No.1風力発電事業者のノウハウで風力発電事業の課題解決を支援~ 〔02/10 ユーラスエナジーホールディングス〕
- 第15回 WIND EXPO【春】2025 ~国際 風力発電展~に出展致します 〔02/10 川崎近海汽船〕
- 自治体のカーボンニュートラル実現を支援するJ-クレジット創出サービスの拡充について~家庭用太陽光発電システムを対象に追加~ 〔02/10 東邦瓦斯〕
- WIND EXPO【春】~第15回 [国際] 風力発電展~出展のお知らせ 〔02/10 ユーラスエナジーホールディングス〕
- 陸上風力発電所のO&Mサービスを提供開始 ~国内No.1風力発電事業者のノウハウで風力発電事業の課題解決を支援~ 〔02/10 ユーラスエナジーホールディングス〕
- 石炭輸送船「能代丸」のバイオディーゼル燃料による試験航行実施について 〔02/10 東北電力〕
- 伊方発電所における通報連絡事象(令和7年1月分)および通報連絡事象に係る報告書の提出について 〔02/10 四国電力〕
情報提供:JPubb