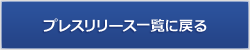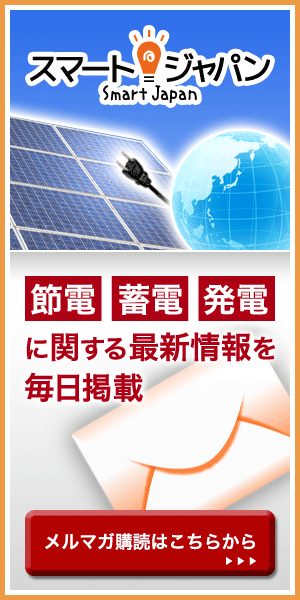プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
佐賀県知事記者会見 2025年01月24日 ・オスプレイ(その1) ・吉野ケ里遺跡公園キャンプ場整備 ・賃上げ ・「ひとりで悩まないで 性暴力救援センターに相談してください」 ・「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」(その1) ・「現代につながる国の骨格を創った 江藤新平復権プロジェクト」 ・有明海再生 ・「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」(その2) ・洋上風力発電 ・嬉野温泉 ・オスプレイ(その2)
令和7年1月24日 知事定例記者会見 質疑(全文)
最終更新日:2025年1月24日 <目次> 1 オスプレイについて(その1) 2 吉野ケ里遺跡公園キャンプ場整備について 3 賃上げについて 4 「ひとりで悩まないで 性暴力救援センターに相談してください」について 5 「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」について(その1) 6 「現代につながる国の骨格を創った 江藤新平復権プロジェクト」について 7 有明海再生について 8 「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」について(その2) 9 洋上風力発電について 10 嬉野温泉について 11 オスプレイについて(その2)
オスプレイについて(その1)○佐賀新聞 発表項目じゃないんですけれども、九州防衛局の対応についてお尋ねします。 昨年11月に米軍オスプレイが福岡空港を利用した際に、防衛局が福岡県に対して、報道機関への回答は控えるようにというメールを送っています。行政側の対応を縛るようなメールかなとは思ったんですけど、知事はかねてより、国と県というのはそれぞれ、こう言ったからこうだと言うべきではないというふうに、独立した存在であるということをおっしゃっていたと思うんですけど、こういう対応をどのように受け取っていらっしゃいますか。 ○知事 私もそのニュースを聞いたときに、佐賀県にもその情報は来なかったのかと確認したところ、同時に佐賀県にもその連絡が来ていたらしいんですよ。その行政の縛りというものについては佐賀県にはなかったということでした。 佐賀県はこういう県なので、フラットに、できる限り公開しながらやっていくという考えをずっと防衛省には伝えていながら、信頼していただくことが何よりも大事なので、真っすぐに仕事していこうと言っていたので、私はその成果で佐賀県にはそういう注釈がつかなかったのだと信じたいというか、そうであればいいなと思っておりますけれども、防衛省さんと福岡県さんとの関係がどうであったのかということにも関係するので、それは防衛省さんがそうやって考えられたのかなと認識しました。 ○佐賀新聞 昨年末に、陸自オスプレイの飛行再開に関しての県庁のほうにも説明がありました。そこで、機体の安全性について、特定の飛行時間を上回るまで一定の条件から飛行を制限するというような説明があったと思うんです。ちょっとその説明が何かよく分かりづらいなという印象を持ったんですけど、知事はこの一連の説明を受けて、どのような認識を持たれましたか。 ○知事 私も最初に、飛行時間、普通、新しいもののほうが磨耗もしていないしと思うじゃないですか。でも、今回は一定の飛行時間を満たしていないほうについて追加的措置という話だったので、それをもうちょっと分かりやすい言い方で説明してほしいなというふうには申し上げております。 しかしながら、いろいろあるんだと思います。むしろ使っていって、慣れていったほうがある程度くせもついているというところも、何となく合点がいったわけじゃないけれども、いずれにしても、そこが原因だというんであれば、そこに対する対処をするというのは大切なことなので、私はできる限り、であるならば、最初に来た機材が、新車が慣れるまであまり外に出さずに敷地内でいろいろ点検をしながら徐々にとか、そういったことを考えていただいているんだろうなというふうに思うので、それについては一定の受け止めをさせていただきました。 それと、常々申し上げている米軍との連携、それについては何かだいぶ前に進んだような気もいたしますので、何といっても機体の安全というものが、我々にとっても防衛省さんにとっても大切だと思いますので、そこは随時、先ほどお話があったような、しっかり胸襟を開いた意見交換をしながら、そして、その姿を皆さん方に示していくという基本の姿をずっと貫いていきたいと思います。
吉野ケ里遺跡公園キャンプ場整備について○佐賀新聞 もう一点なんですけれども、県が吉野ヶ里のほうでキャンプ場をつくるという計画をされています。これについて、考古学者のほうから遺構への影響を懸念する声が上がっています。このことについて知事はどのように対応と受け止めをされていますか。 ○知事 先ほどから文化の話を散々しましたけれども、今の佐賀県庁はとても文化とか、あと遺跡とか、そういう我々が、佐賀がずっとこれまで培われてきたものはとても大切にしてきたと思っています。今までそれこそ道路を引くときにも、文化財というのはある程度大切にしないきらいもあったので、だいぶそういったところは私からも、何といっても文化がまず大事だからというふうに言い聞かせて運営をしてきたわけです。石棺墓のときも、何よりもそういったものの威厳というものを大事にしながら埋め戻すということもしましたしという認識を持っています。 それでも、この吉野ヶ里の問題に関していいますと、そういう遺跡を大切にするということと、みんなに見ていただきながら公園を利活用していくという部分、そこをしっかりと両立する形で成し遂げなければいけないな、みんながハッピーになるようになればいいなと思いながら作業を進めています。 そうした中で、もちろん考古学者、歴史の関係の皆さん方からは懸念の声があることも分かっていますし、そういったことを踏まえながら、これまでもいろんな修正もしてきましたし、これからも両立を図っていくという上では、県は考古学者の皆さんだけではなくて、いろんな皆さん方の意見を踏まえながら前へ進めていくという姿勢で臨んでいきたいと考えています。
賃上げについて○時事通信 まず、賃上げについて伺いたいんですけれども、最近、都市部の大手企業さんのほうでは初任給引上げの動きというのが多く出ております。佐賀県も含めて、地方の中小企業にとってはただでさえ厳しい人材獲得競争の中で、こうした動きがあるとさらに厳しい状況にさらされるかと思います。 県のほうもこれまでも賃上げですとか人材確保への支援というのを積極的に行ってきたと思うんですけれども、今後の支援についてどのように考えているかを教えてください。 ○知事 そうですね、全体として見て、この国自体の賃上げが必要だということは私も賛成です。ですので、佐賀県もずっとここのところ非常に大きな賃上げを実現して、最低賃金を上昇してきましたけれども、だんだん上がりまくってくると、そこの課題も見え隠れするわけで、1つは地方の中小企業がそこにどこまでついていけるんだろうという状況と、例えば、都市部と地方との間の格差、結局、多くのみんなは地方部で育ってきたのに、都市部に行って高い賃金をいずれ大人になって受けるようになってという課題と、今、(全国農業)担い手サミットをやっていましたけれども、だったらちゃんと我々が作った農水産物を価格に転嫁してくれよという思いが強くありますし、野菜が値上がりしたとか、卵が高くなったと言いますけど、どれだけ我々が苦労しながら生産しているのかという、国全体として様々な格差というものに対処しながら、みんなが今よりもハッピーになって全体としての賃上げ、そして様々な生産物に価値がついて、それに見合った値段がつくということを全体として取り組まなければいけないと思いますので、ただ単に、安易に突っ走っていくと、そこのひずみというものが出るので、社会全体で様々なそういったもののひずみが起きないように、そして、地方部にも賃上げ、そして企業価値の連鎖が行われるように我々は取り組んでいかなければいけないと思うし、国に対しても訴えて、世論にも喚起していきたいと思っています。
「ひとりで悩まないで 性暴力救援センターに相談してください」について○時事通信 もう一点、性暴力被害の支援について伺いたいんですけれども、女性の場合だとこういった支援を充実していって、あとは女子トイレの個室ですとか、あとは婦人科検診の際ですとか、そういった情報にアクセスする機会というのは非常に多いと思うんですけれども、男性、男児の被害に遭われた方は、なかなかちょっとトイレの個室だったり、病院に行くですとか、そういった情報にアクセスできる機会はなかなか少ないと思うんですけれども、その件に関してはどういったふうに啓発していきたいとか、積極的な広報ですとか、それについてちょっとお考えをお聞かせください。 ○知事 やはり今一番大きな課題は、男性、男児がそういう被害に遭ったときに声が上げにくい、アクセスポイントが少ない、しかも、それに合わせるような医療機関というものとの連携、男性の場合の医療専門科目があるわけで、そういったところのつながりというのができていなかったので、今回はみんなが気持ちを一つにして、男性、男児、声を上げて、ちゃんと相談に乗るからねという体制ができたので、これをみんなに伝わるような形でいかに広報するのかということが大事だと思いますので、我々もまだこれは始まったばかりでもあるから、ぜひ報道の皆さん方もそういった、真に困っている人たちにこういったアクセスポイント、相談窓口があるということをぜひ周知いただくように御協力いただけたらありがたいと思っています。 ○時事通信 もう一点、そしたら、男性の性暴力被害に関して、現在、県内のほうで何件ぐらいあって、女性等を含めて全体の何%ぐらいが男性の被害の相談があるのか、ちょっと教えていただけますか。 ○知事 答えられるかな。 ○県職員 令和5年度の支援実績になりますけれども、性暴力、性犯罪被害の関連の相談が延べ件数で大体265件ほどございます。うち男性からの相談が11件というふうに実績としてございます。 ○知事 あと詳細は後で部のほうでお願いします。 ○時事通信 ありがとうございます。幹事社からは以上になります。
「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」について(その1)○日経新聞 冒頭の佐賀県立大学の学長就任予定の山口先生についてお尋ねします。先ほどなるべく早く具体的な準備に入るために早く発表したというふうに御説明していただきましたが、実際、山口教授のほうに正式に打診されたというか、お受けいただくに当たってのオファーをしたのか、それとも、多分初めて去年プロジェクトを立ち上げた段階で、もう既にそれはお伝えしていたのかという辺りと、あと、山口先生の現状の今のポジション、だから、これに就任予定者となることでもう立教大学のほうは完全に離れられるのかとか、そういうふうな、今後どういう立場で活動、準備されるのかを教えてください。 ○知事 山口さんにリーダーをやっていただいたときからずっと一緒にやっていただきたいなと思いながら仕事をしてまいりましたけれども、今、長谷川さん(日経新聞)が言うように、人生のかかったことなので、改めて正式にオファーをさせていただいたのが1月7日に2人で話をして、こういうふうに学長予定者になっていただきたいとお話ししたところ、ご快諾をいただいたと。一緒にやりましょうということでありましたので、では、早めに発表しようということになりました。もちろん、今、立教大学の教授であられますので、当面は立教の先生でありながら、予定者ということでやられると思いますけれども、どこかのタイミングでこちらのほうの専任になっていただくという流れかなと思います。具体的なスケジュールについては、これから開学を見据えて、山口先生と話し合っていきたいと思います。 ○日経新聞 関連で一つ確認ですが、その1月7日に山口先生と2人でお話をされたというのは県庁でですか。それとも、ほかの場所で。 ○知事 県庁だったと記憶しています。県庁だよね、あれね。はい、県庁です。 ○日経新聞 ありがとうございます。
「現代につながる国の骨格を創った 江藤新平復権プロジェクト」について○朝日新聞 発表項目で一つ伺いたいんですけど、江藤新平の復権プロジェクトがありましたけれども、知事、今年就任10年目を迎えて、これまでを振り返っても、明治維新から150年というタイミングもあってということかと思うんですけれども、かなり維新期の関係に力を入れておられるのかなと思うんです。そこで、今の日本のそういう骨格につながるものをつくったという意義があってということだとは思うんですけれども、その維新期に光を当てることの意義と、そこと県政として力を入れることで、今の県民が、県全体にどういう意義があって、どういう効果を期待されているのかということをちょっと伺います。 ○知事 やはりまずは佐賀の問題から言うと、やはり自分の地域に誇りを持っているかどうかでその地域がどうなるかということに大きく左右するとずっと私は知事になる前から思っていて、全国でもうまくいっているところはやはり自分の地域を誇らしく人にしゃべれるエリアなんですよ。なので、我々が恐れているのは、誇りの空洞化だったり、心の過疎だったりするので、そうならないようにと思ったときに、佐賀は何でんかんでんあるわけですよ。なので、ただ、この国の礎をつくったのは佐賀であるわけで、とってもその当時の佐賀県の人たちって、特に八賢人を中心に鳥瞰力がある。要は、今まで江戸時代はこうだったからじゃなくて、どうあるべきなのかというのを全く違う世界から紐解くわけですよ。 例えば、江藤新平の裁判の制度だって、それまでは、要は官が裁いていたわけですよね。“おいおい、控えおろう”みたいな感じで。そうじゃなくて、裁判ってもっと民衆の苦しみを救うようなものであるべきじゃないのかなんてことを言ったり、何でお医者さんの子どもがそのままお医者になるんだよと。ちゃんと免許制度をつくろうよと言ったのも佐賀だし、そういう、何もないところから制度、システムをつくっていくというのに佐賀はとてもたけている地域だと思うんですよ。 ただ、やっぱり、あまりやり過ぎちゃったのか、なんかちょっと佐賀は、後からどんどんやり過ぎて、空気読んでいないんじゃないのみたいな雰囲気になったのか分からないけれども、結局、佐賀は断罪をされて、佐賀戦争に至って、しかも、県も取り潰しになったわけで、そこをちゃんと県民がみんなで共有できたら、実はここってすごい県なんだなというアイデンティティーが確立されるかなと思って、私10年、その仕事を一つ大きな柱としてやってきたんです。 もう一点言うと、それって実は今の時代、地球上がこんなガラガラポンで、価値観が何かも分からないような迷走している時代に、今までこうやってきたから、昭和のときからずっとこういうシステムでやってきたからだめなんだと僕は思うわけです。全く違う、どうあるべきなのかをみんなで考えてつくり上げていくという、想像力というかさ、全体を見回しながらという力がとても必要なので、それをみんなで考える大きなきっかけにこの佐賀の明治のときに新しいシステムを作ってきたというのは生かされるのではないのかなと思うので、佐賀のためでもあるけれども、この国のためにも佐賀の礎を築いてきたここに焦点を当てるというのは大変意義深いものではないかと考えております。
有明海再生について○毎日新聞 農水省が有明海の再生加速化として、交付金を新設して、10年で100億円という方針を示していますけれども、改めてこちらの交付金に対する知事の受け止めをよろしくお願いします。 ○知事 私はずっと地元負担なんてあり得ないという話をずっとしてきました。もともと和解するために補償しようということで、開門しないということの前提で有明海漁協さんなどが苦渋の決断で未来を見るためにということだったわけですよ。それを地元負担ありという議論自体がおかしいと申し上げてきたんだけれども、ただ、今回はそうは言いながらも、農水省さんはそういったことも受け止めて、うちの県関係の議員たちも、そこは同じ意見になって国に対して伝えて、農水省は農水省で努力をして、よく財務省とも相談しながら、交付金という形であればって、いろんなことがあったと思います。私も霞が関にいたので、簡単にできるものではないけれども、でもその方向になるような努力を積み重ねてきたということに対しては敬意を表したいと思いますし、やはり農水省ともそういう関係が築けそうな、先だって担い手サミットもやりましたけれども、いい関係が構築できて、結果的に我々みんなが望んでいる有明海の再生というものに結びつくことが少しでもできればという気持ちであります。 ○毎日新聞 交付金に対する10年で100億円という金額ですけれども、そこら辺の効果、再生に対する効果としてはどういうふうに思われますか。 ○知事 もともとの100億円というのは、そもそも国のほうから提示された額でもあります。これは4県合わせてという数字なので、これがどの程度の効果を出すのかなというのは未知数。ただ、何でんかんでんやらんばいかんというのはみんなの共通した気持ちなので、それこそ、海底耕うんだったりとか、二枚貝の種苗をしていくとか、いろんなことをやっていくんでしょうけれども、それがどういう効果になっていくのかということ、それと、もともと基金という話だったけれども、今政府が基金をつくるのはなかなかきついらしいんですよ、今の様々な政治情勢から。ということで、みんなの知恵を合わせた中で交付金、交付金ということはどういうことかというと、自分たちでやることを決めてということですよね。単にお金が積まれるんじゃなくて、そこまではオーケーしてくれるから、自分たちでやることをまとめていかんばいかんわけですから、そういったことでもみんなでこれからそういった意味では有明海の関係者が集まる機会は非常に多くなると思うので、そういったこと一つ一つが光が見えることにつながっていけばいいなということで期待しております。 ○毎日新聞 関連で、漁業者の中には開門調査を求める声もありますけれども、知事も昨年2月、漁協が賛同の意向を示したときにも開門調査が必要だという気持ちは変わりがないというお話をされていましたけれども、知事の開門調査に対する姿勢なり考えなり、変化はありますか。 ○知事 いや、それはずっとあのタイミングから全く海況が変わってしまって、みんな苦しんでいたわけで、それが改善はされていないので、調査は必要だという思いは、あれはみんなの中で消えようがないと思うんですよ。私は今でもよくそういったことを漁業者の皆さん方から言われることもありますし、これだけこういう歴史を繰り返してきているので、そこはみんなにその思いというのは消えないと思うんですけれども、そういった中で、今回、苦渋の決断で再生事業ということになっているので、それはみんな心に思いつつも、たまにそういったことも、だよねと話をしつつも、前に行くということなのかなというふうに思います。
「佐賀県立大学(仮称)の学長予定者」について(その2)○読売新聞 発表項目の県立大学の山口リーダーの学長予定者のことに関してなんですけれども、念のための確認ですが、今、学長予定者という名前になっているかと思うんですが、これは予定者が取れるのは令和11年4月の開学をもって学長というふうになるという理解でよろしいでしょうか。 ○知事 はい、令和11年4月か。 ○読売新聞 それまでは学長予定者ということでずっと呼称としては続くということですか。 ○知事 はい。まだ大学はできておりませんので。 ○読売新聞 もう一点が、今回、学長予定者に選任した人選の一番評価している部分というのは、ここにも愛着であるとか、チームリーダーとしての役割とあるんですけれども、具体的に知事から見られての山口学長予定者の評価というところは改めてお願いできますか。 ○知事 もちろんここにありますような、すごい大学教育に対する強い思いだったり、熱量だったり、専門家チームの会合の中でも非常に前向きな議論ができているという理由がまずあるわけだけれども、それともう一つは、やはり私は学はすごく独立性が必要だと思うんですよ。私が言うのもなんだけど、行政とべたべたじゃいけないと思うんです。やっぱり自分たちとしての主義主張というのをつくっていく、それがひいては佐賀のためになるんだけれどもというような部分が大事なので、この1年間、リーダーとしてやっていただいていて、もちろんいろんな議会に呼ばれたりとか、いろんなことを山口リーダーがする中で、当たり前のことだけど、別に県庁だったり私に忖度することなんか全くないし、自分の思いでやられているということ、そういうことがこの1年間でさらに強い確信に私もなったので、ああ、このまま佐賀への強い思いの中で学者としての誇りを持ちながら、大学としてどうあるべきなのかという新しいゾーンを切り開いていっていただけるのではないのか。もちろん県立大学だから、私も佐賀県としてやってほしいことは言うけれども、でも、最終的な学の判断というのは学長にあるというところで、いい関係が築けるんではないかと思った次第です。
洋上風力発電について○日刊工業新聞 洋上風力発電についてお伺いしたいんですけれども、今日、唐津のほうで県内事業者向けの勉強会も開かれるということなんですが、地元企業のサプライチェーン参入であったりとか、あるいは設備投資の補助であったり、うまくいけばそういった市場が1つ新しくできてくることになると思うんですけれども、そこら辺の補助であったりとか支援のお考えであったりとかをお伺いできればなと思います。 ○知事 もともと洋上風力については進めていこうということで我々も進めていますけれども、なかなか有望区域にプロセスの中で様々な課題が水産庁ほかから言われているので、それについて真摯に取り組んでおります。 ただ、その過程の中で、関係者がいろいろまとまりつつあるのかなというところというのは感じるところもあるので、これから起こる課題に一つ一つ丁寧に対応して、県外の方もいろいろ心配されている方もおるので、そういったところについても話をしながら前に進めていきたいと。その中で起きた課題については対処していきたいと思います。そのやり方についてはこちらのほうでも考えていきたいと思います。
嬉野温泉について○読売新聞 嬉野温泉のことでお聞きしたいんですけど、現状、嬉野温泉の観光客が増加したことに伴って、源泉の水位が低下しているという事情があって、今ちょうど現地の方々が源泉保護の取組をされてあるというところなんですけど、知事として、佐賀の観光地としても重要なスポットである嬉野温泉で、そういう源泉の水位が低下しているということを聞かれたときのを受け止めをまずお聞きしたいのと、県は、温泉法で知事が温泉の保護の必要性がある場合は採取制限をかけるという権限を持っておられると思うんですけど、そういう保護をする立場として、今後、嬉野温泉の保護について県としてどのように携わっていかれたいかというのをお願いします。 ○知事 嬉野温泉は、みんなが思っている佐賀県の大切な資源で、それに対する、今、みんなのいろんな思いがあると思います。私がこの水位がだいぶ下がっていると聞いたのが半年ぐらい前だったと思うんです。そのときに私が考えたのが、県は温泉法を所管しております。嬉野温泉がずっと大切に残っていくということが何よりも大事だから、いわゆる規制庁として規制するという立場で粛々と対応するようにと担当に話しました。なので、いろんな声があっても、もう客観的なデータで冷静に、実際、最悪の場合については、今お話しになったようなことも、権限もあるわけですけど、そうならないように、みんなで資源を守っていこうという形になればいいわけだから。ただ、我々はそこについてのデータを示して、客観的なデータで、規制庁としてこうなったらこうなるよというところを示して、皆さん方にしっかり自主的に対処できるようにということで考えています。 ですので、あくまでも、本当に、なくなってしまうなんてことはあり得ないから、なくしてはならない大切な財産だからこそ、みんなで協力して守っていくという体制がこれを機にできることを期待しています。
オスプレイについて(その2)○西日本新聞 オスプレイに関してなのですが、本日報道で、1日当たりの離着陸回数が改めて16回というのと、夜間は5回という説明が防衛省のほうからなされたという報道がありましたが、この件のまず事実関係についてはいかがでしょうか。 ○知事 まず、今、7月に向けて、公害防止協定に基づく事前協議を行うことにしていて、今そのための事前の調整を行っている途中ということです。ですので、今、様々なやり取りをやっているわけですけれども、今日の、例えば、着陸回数とかそういうことに関しては、どういうことかということで担当部に聞いてみましたが、防衛省に詳細を確認したところ、表現方法が異なるだけで、実質的に同様の内容であったと報告を受けたと私は聞きました。 ですので、数字自体の作り方の問題で、基本的には同じことを言っているんですよ、と言われましたというふうに聞いております。いずれにしても、今その調整の過程でありますので、その詳細については部のほうに聞いていただければというふうに思います。ありがとうございます。 |
- 次世代営農型太陽光発電システムが令和6年度新エネ大賞「新エネルギー財団会長賞」を受賞 〔01/30 出光興産〕
- 【当社初オンサイトPPA】種子島宇宙センター電力購入契約(PPA)による太陽光発電設備等導入事業 - 再エネ電力の供給開始に関するお知らせ 〔01/30 九電工〕
- リケンNPR株式会社による風力発電所を活用したオフサイト型コーポレートPPAサービスの導入に関する契約締結について 〔01/30 東北電力〕
- KDDIとJパワー、陸上風力発電所に係るバーチャルPPAを締結~再生可能エネルギーの活用で通信事業における脱炭素化を推進~ 〔01/30 電源開発〕
- KDDIとJパワー、陸上風力発電所に係るバーチャルPPAを締結 〔01/30 KDDI〕
- 都市ガスデータ配信サービス「アイチクラウド」 提供開始のお知らせ 〔01/31 愛知時計電機〕
- 2025年3月分電気料金の燃料費等調整について 〔01/30 中国電力〕
- 2025年3月分電気料金の燃料費調整等について [東京電力エナジーパートナー株式会社] 〔01/30 東京電力ホールディングス〕
- 柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更認可申請の補正書の提出について 〔01/30 東京電力ホールディングス〕
- 代表取締役の異動(社長交代等)に関するお知らせ 〔01/30 東邦瓦斯〕
情報提供:JPubb