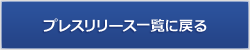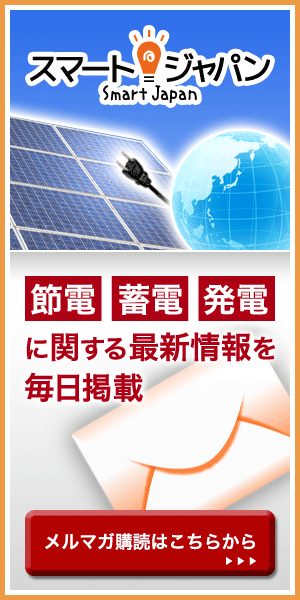プレスリリース
powered by JPubb本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
作業船ハイブリッドシステムを更に進化させる「発電機自動発停制御システム」を開発
「発電機自動発停制御システム」を開発
2013年04月30日
東亜建設工業株式会社(東京都新宿区:社長 松尾正臣)は、深層混合処理船の更なるエネルギーの効率化を目的に「発電機自動発停制御システム」を開発しました。
開発の背景
当社が平成22年3月に建造した深層混合処理船「黄鶴」に搭載された「作業船ハイブリッドシステム(※1)」は、エネルギーの効率化と自然エネルギーの利用を組み合わせたシステムで、従来の作業船に比べ、CO2排出量削減ができる構造となっていました。
(※1)①②③④より構成
作業船において、初の試みとなったこのシステムは、その後、燃焼促進効果のある燃焼改質装置を組み込み、システムの改善を図ってきました。
この作業船ハイブリッドシステムに、今回開発した「発電機自動発停制御システム」を連動させることにより、更なるエネルギーの効率化とCO2排出量削減を実現することができました。
【作業船ハイブリッドシステム】
① 発電設備・統合制御装置
複数の可搬式ディーゼル発電機を設置することで、発電機にかかる負荷を分散させるとともに、作業内容に応じて最適な台数を効率的に稼動させることができます。
② 電力回生システム
作業船本体から、深層混合処理機を下降させる際に、昇降ウインチが回転することによって発生する電気を発電機側に戻す(回生)ことにより電気を再利用することができます。
③ コージェネレーションシステム(※2)
作業船で使用する電気を発電する際に発生する排熱を回収して温水をつくり、船内で使用する温水として有効利用します。
(※2)燃料を用いて発電するとともに、その際に発生する排熱を冷暖房や給湯、蒸気などの用途に有効利用する省エネルギーシステムのこと。
④ 太陽光発電、風力発電
可搬式ディーゼル発電機による発電に加え、太陽光発電、風力発電を採用し、船内照明等の電力として利用しています。
また、太陽光発電では、可変式太陽光パネルによる太陽光追尾システムを搭載し、効率的に蓄電することができます。⑤ 燃料改質装置
人体及び自然環境に悪影響を与えない程度の極低レベル放射線(β 線・γ線)を照射する特殊セラミックスが内部に格納されており、装置の中を燃料が通過することにより、燃料の分子レベルでの改質が行われて燃焼促進効果が発揮されます。
燃料改質装置は、陸上運搬車・重機及び海上輸送船では既に多数の実績がありますが、作業船での導入は始めてです。
http://www.jpubb.com/press/image.php?image=52017
「発電機自動発停制御システム」の概要
深層混合処理船「黄鶴」は、従来の大型発電機を搭載した作業船とは異なり、複数の可搬式発電機(800KVA)を並列で運転することにより、船内に電源を供給しています。
「黄鶴」の稼働においては、作業船ハイブリッドシステムを構成する発電設備・統合制御装置により、機関監視室から使用する電力量を監視しながら、使用電力に見合った発電機の運転台数を制御することが可能です。
しかし、運転台数の制御にあたっては、機関部員が、施工中の発電機の負荷変動を常時監視しながら、手動で発電機の起動・停止を行わなければならず、機関部員の作業負担を軽減するため、施工中は運転台数の制御を行うことが困難でした。
そこで、今回開発した「発電機自動発停制御システム」では、現場ごとに行われる試験施工時の使用電力量の変化と土質形状図を参考に施行フローを作成し、予め設定された施工フローに従って運転台数の制御を自動的に行うもので、深層混合処理機先端の撹拌翼が、水中や柔らかい地盤表層部では運転台数を少なく、撹拌翼に負荷がかかる地盤深層部では増やすことができます。
尚、この「発電機自動発停制御システム」は、現在特許を出願中です。
「発電機自動発停制御システム」の制御フロー
「発電機自動発停システム」は、深層混合処理船の運転制御を行う地盤改良操作盤より得られる「処理機の深度情報」と発電設備・統合制御装置から得られる「消費電力と各発電機の運転状態」をもとに予め設定された発電機運転フローに従い、発電設備・統合制御装置を経由して発電機の運転・停止を行います。
「発電機自動発停制御システム」のブロック図http://www.jpubb.com/press/image.php?image=52018
「発電機自動発停制御システム」の特長
(1)施工条件(土質、改良深度、水深)によっては、15%以上の燃費向上が可能です。
(2)複数の発電機に運転時間の偏りが生じないよう、運転の順番が設定できます。
(3)事前の設定を超える使用電力量になった場合、緊急に追加で発電機を運転させる「フェールセーフ機能」があります。
(4)発電機の制御電源を入れ忘れた場合やシステム稼動中に手動で発電機を停止させた場合などにエラーメッセージを表示させる「ヒューマンエラー防止機能」があります。
今後の展開
東京湾の工事で検証した結果、5%を超える燃費向上を確認しております。
また、同じ深層混合処理船である「デコム7号」に搭載した結果、横浜地区の工事では15%の燃費向上を実現しました。
本件に関するお問い合わせ先
東亜建設工業株式会社 経営企画部広報室 清水TEL:03-6757-3821 / FAX:03-6757-3830- 『IE EXPO2013(中国環境博覧会)』(5/13(月)~5/15(水))出展について 〔05/02 オプテックス〕
- 2013 KOBA SHOW出展のご案内 〔05/02 TOA〕
- 第34回「2013日本BtoB広告賞」 3部門で入賞 〔05/01 堀場製作所〕
- シンガポール・ポストからの郵便物自動処理システムの受注について 〔05/01 東芝〕
- 東京電力株式会社のスマートメーター用通信システムの受注について 〔05/01 東芝〕
- インテル コーポレーション役員人事。ブライアン・クルザニッチを最高経営責任者(CEO)に選出 〔05/03 インテル〕
- IBM Research、原子を使った世界最小の映画を製作 〔05/02 日本アイ・ビー・エム〕
- デル、LEDバックライト搭載 10点マルチタッチ21.5インチワイドモニタ「S2240T」を新発売 ~ 高度な柔軟性と利便性でホームユースにもオフィスにも最適なタッチ機能を実現~ 〔05/02 デル〕
- 役員人事のお知らせ 〔05/01 日本アイ・ビー・エム〕
情報提供:JPubb